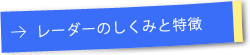「PANSY」という花の名前を冠した、南極昭和基地大型大気レーダーのプロジェクト。そもそもは2000年1月、極地研に着任してきたばかりの研究者が「南極でこんなデータが取れたら、きっと素晴らしい」と夢を語ったことから始まりました。同年5月には、当時最先端の京都大学MUレーダーを手本に、その設計者や極地研のメンバーが集まって、核となるプランが一気に作り上げられたといいます。そして2002年には、朝日新聞の一面や科学雑誌『Nature』の取材記事として報道されるなど、世界的にも大きな注目を集めました。しかし実際にプロジェクトが動き始めたのは、発案から約10年後。そして2011年、念願の初観測が実現しました。ところが、そのあと南極は記録的な大雪に見舞われます。しかも2011〜12年、南極観測船「しらせ」は2年連続の接岸断念という非常事態に……それでも「PANSYは面白い」と言うのは、東京大学の佐藤薫教授。2000年、新任助教授としてPANSYプロジェクトを発案し、2005年からはその代表を務める佐藤教授に、リサーチコモンズ「地球環境データ」プロジェクト(2013年度〜)と関わる話題を中心にお聞きしました。
理論にたえる大量データを生み出すようになった観測機
地球物理学は、たとえば素粒子物理学などのように、高度な数学を駆使して現象を理論的に突き詰め、非常に緻密な実験によって理論を検証していく分野とはかなり違います。かつては1、2回の観測から得られたごく少ない情報だけで議論が進められることもありました。しかしPANSYは、「理論にたえるデータが出せる」観測機なんです。鉛直分解能150メートル・時間分解能1分の高解像度を持ち、データを見ただけで「何だろう、これは?」と思わせるような、大気の表情が浮かび上がってくる。仮定を置くことなく理論と結び付き、新しい発見が生み出せるような、非常に大量なデータなんですね。

高解像の観測・モデル・理論をむすぶデータ中心科学
一方、大気の現象を解くためには「モデル」が使われます。大気物理学では、たとえば天気予報にもそのためのモデルがあって、スーパーコンピューターを使って大規模なシミュレーションが行われています。このようなシミュレーションのデータと、観測が生み出すデータは、どちらも大量なため直接比較することができません。さらに、このような高精度なデータから解明が期待される現象には、その礎となる気象学的な理論自体も作らなければならない場合がほとんどです。これは、大量データから法則を発見するのとは違って、第一原理としての運動方程式から組み立てていく、いわば"紙とペンでつくる"新理論であり、それぞれのデータに適用することでその解析を大きく進展させることができます。この観測データ、シミュレーション、新理論の3つが揃ってこそ、高解像度観測時代のサイエンスは面白くなる。そして、この3つの中心にあって、データ解析を担うのが「データ中心科学」です。私たちの研究室では今、この発展を目指しています。

解明が待たれる大気の小さな構造「重力波」
ところで2006年4月頃、私たちは海洋研究開発機構の研究者とも共同でスパコン「地球シミュレーター」を使って、PANSYの仕様に合わせた全球3年分のシミュレーションを始めました。計算には2年を要しましたが、鉛直の広がりが80キロメートル・鉛直解像度が300メートルの仮想大気空間で繰り広げられる大気の様々な階層構造を再現したシミュレーションは、少なくとも7〜8年間、世界一でした。中でも私たちが知りたかったことのひとつに「重力波」と呼ばれる、大気の中にある非常に小さな現象があります。「気象ノイズ」と呼ばれていたのですが、80年代の半ばにこの効果を計算に入れたら天気予報の精度が格段に向上し、その重要性が広く知られるようになりました。私たちはこれをシミュレーションデータの解析によって詳しく調べていたのですが、実は予想外の特徴も見えてきまして、この重力波の伝播経路には集中する場所があり、それがなんと極域、まさに昭和基地の真上に位置することがわかったのです。

極域だけに見られる美しい2つの雲のサイエンス
観測に適した南緯69.0度、東経39.6度に建設されたPANSYは、2015年3月からは、1045本のアンテナによるフルシステムで観測を行っています。省電力に徹してつくったため、連続した大規模観測データが長期間にわたって取れるレーダーであることも、世界的に際だった特徴です。PANSYを使って解明を進める重要テーマには重力波の他、オゾンホール、南極特有のカタバ風、宇宙からのエネルギーや物質流入に関わるオーロラ、極域固有の2つの雲などがあります。雲の1つは、冬の成層圏約20kmの高さにできる「極成層圏雲」です。ピンクやオレンジ色に輝く美しい雲ですが、その表面でフロン起源の物質を化学変化させオゾン層を破壊する恐ろしい作用があり、この雲の量がオゾンホールの大きさを決めています。もう1つは最も高い約90kmの上空で夏に発生する「極中間圏雲(夜光雲)」です。1885年以前の記録がないことから「人間がつくった雲」と言われ、雲の生成量が敏感に温度に反応して気候変動を映し出すことがわかっています。PANSYを中心に、昭和基地にあるさまざまな光学・電波(中波、ミリ波、レーザー等)観測をつないで、たとえば重力波の持つ風と温度、鉛直構造と水平構造をそれぞれ同時に捉えるなど、南極大気現象の多角的理解を進めています。

北極と南極をつなぐ、観測機をモデルでつなぐ
南極における大気現象の解明は、グローバルな大気循環の出発点や終着点になっている点で重要であることはもちろんですが、南極の研究で北極の大気が理解できる、あるいは北極と南極の大気状態は連動していることなども徐々にわかってきています。そこで今、取り組み始めている新しい夢は、地球上にあるいくつかの大型大気レーダー拠点をつないで同時観測しよう、ということなんです。非常に小さな現象を捉えようというわけですから、局所的なものであって、同時観測しても意味がないのではないか?……と最初は思っていました。しかし2006年に開発された私たちの全球モデルを土台にして、もしこれにリアルな地球の観測データをつなぎ、地上から中間圏までの大気状態を再現したら、画期的なシミュレーションになることは間違いありません。ちなみに北極の成層圏で、数日で50度ぐらい気温が上がることのある「突然昇温」という現象が知られています。起きる頻度は3年に2回ぐらいですが、いったん起これば中緯度の状態も変わり、赤道も変わり、南極も変わります。このようなダイナミックな大気循環を世界同時の高解像度観測によって捉え、地球規模の気候変動機構の解明に貢献したいと考えています。

(文:佐藤薫・池谷瑠絵 写真:水谷充 公開日:2015/06/10)