ゲノムはどんな意味を持つのだろう?
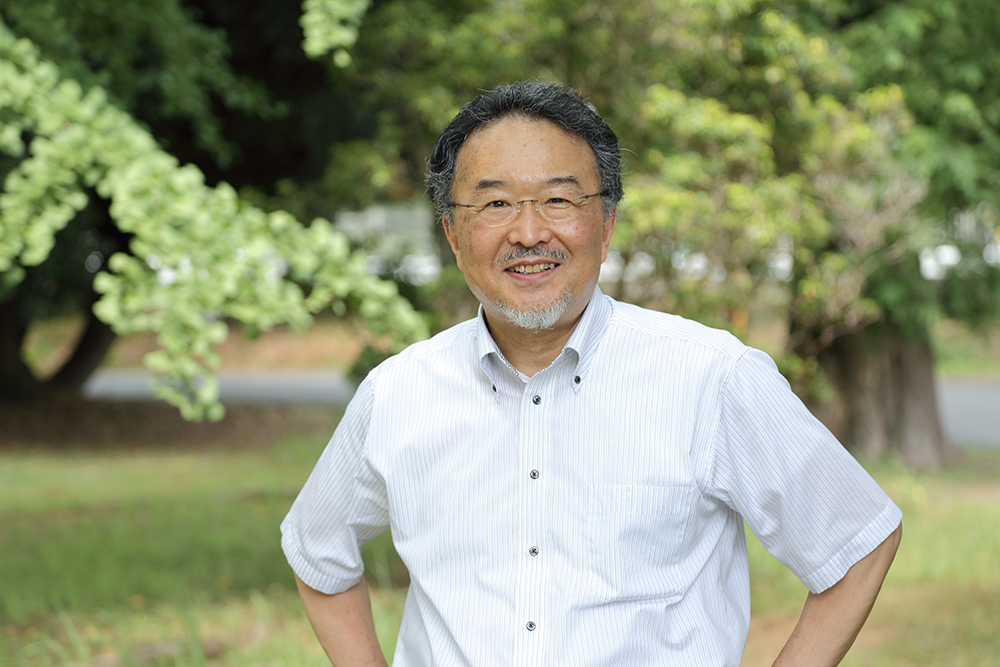
答える人:小原雄治特任教授(国立遺伝学研究所)
国立遺伝学研究所 特任教授、ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)センター長、新学術領域研究「先進ゲノム支援」研究支援代表者。1974年京都大学理学部卒、1988年英国ケンブリッジMRC分子生物学研究所客員研究員等を経て、1996年より国立遺伝学研究所教授、2004〜2012年 所長を務める。分子生物学の発展を背景に、生物の表現型とゲノムを結ぶメカニズムを追求する遺伝学の発展に尽力。また研究の発展には、これらのデータの収集・共有が必須であることから、統合データベースの構築・整備に注力する。DBCLSホームページはこちら。
イノベーションは5年に2回起こる
ゲノムを研究するゲノミクスの分野は、国際的にも競争が激しい分野だ。研究を支える技術的な発展も目覚ましく、国立遺伝学研究所 小原雄治特任教授(DBCLSセンター長)によれば、「5年の間に2回ぐらい、イノベーションが起こる」という。ゲノムを読み取るために広く使われる世界標準的な装置にも変遷があり、「新しいマシンが利用可能になるが早いか、即対応していかなければならない」。それはつまり、ラボでどんな実験を行い、どんな試料を用意し、どんな解析を行うか、という研究の一連のプロセスが再検討されなければならないことを意味し、しかも各段階に高度な専門性が要求されるという。一方で、ゲノムを必要とする研究領域は拡張の一途だ。「昨日までゲノムなんて関係なかった研究者が解析したいというケースが増えている」と、小原特任教授。「環境、医学、農学などの分野が多いですね。例えば土や川の微生物を調べたら、ゲノム解析によって面白いことが分かってくる。医学では病気遺伝子はもちろん腸内細菌など、農学では品種改良のために、栽培植物のゲノムを調べたい……」など、さまざまな要望があるという。シングルセルのゲノム解析(→008を参照)も急増しているそうだ。

ゲノムという研究分野を全体として支援する
このようなゲノム研究の展開に対応するためには、個々のラボで対応するよりも、規模的にもまとまって専門性の高い機能を提供し、装置のアップデートも集中的に行えるような体制を組むことが望ましい。そこで、我が国の学術研究の中心的な競争的研究資金である「科研費」に採択された研究を対象とした公募により、そのゲノム解析の部分を支援する研究事業が始まった。「2000年に科研費の特定領域研究に支援班ができたのが最初です。その機能が新学術領域研究「ゲノム支援」となり、さらにリソースや技術をもっと分野横断的に提供できるよう組み替えられ、大学共同利用機関である国立遺伝学研究所を中核機関とした、現在の体制につながっています」。小原特任教授は現在、その新学術領域研究「先進ゲノム支援」で、研究支援代表者を務める。個々の大学等では整備・維持が困難な最新の設備・技術を常に整備し、国際競争の激しい最先端研究のゲノム解析を担うなど、メンバーとともに支援依頼者の要望に応えてきた。「新しい装置を試す中で、ゲノムを読み取るラボの技術もどんどん上がっている。またビッグデータ解析ができる情報系の研究者達が実データを扱うことで、情報解析のスキルが向上していく。支援を依頼した研究室の学生が1週間ぐらい滞在して、オンザジョブトレーニングを行う──と、さまざまなかたちでの好循環を目指しています」。
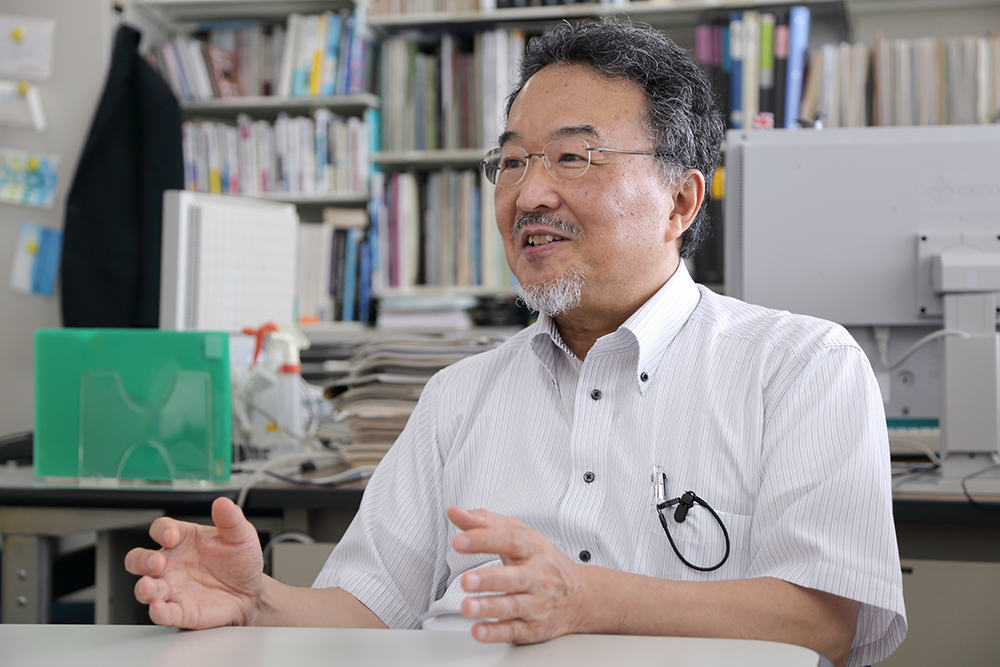
ライフサイエンスのデータベースの重要性
ところでゲノムは元来、個人を識別する生体情報という、個人情報保護や研究倫理の観点からも慎重な取り扱いを要する特殊なデータである。一方、ビッグデータでもあることから「やっぱり集めたほうが勝ち」という側面もある。小原特任教授は言う──「米国だけでなく、例えば中国などにも大規模なゲノムセンターがあり、解析サービスも行っています。当然ながら、データはサービスの提供側に集まる。ここに、日本が学術としてデータを持たなければならない理由があります」。またデータは関連づけられていないと活用できない。「例えば医学なら、ゲノムとエピジェネティクス、あるいは医療記録との関連づけなどが必要です。『僕らはゲノムでできている』のだけど、ゲノムだけでは決まっていない。生き物も含めその内外全部のゲノムを取得・解析する分野を「ホロゲノム」と言いますが、そのように見ていくと、実際には寄生されていたり、腸内には細菌がいたりといった環境を含めて生き物は成立しているんですね。するとどこまでが「僕ら」なのか、生きていくための単位が変わっていく可能性がある。生命とは何か、個と種はどこで区別されるのかといった根源的な問いに答えられる日も来るのではないでしょうか」。

原核生物からヒトまで「ナショナルバイオリソースプロジェクト」
ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)情報公開サイト
NBRPのリソースを利用した研究論文は、現在およそ2万8,000本にも及ぶ。
ライフサイエンスの基盤となる、研究開発の材料としての動物、植物、酵母や大腸菌などの微生物等をバイオリソースという。ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP、プログラムスーパーバイザー:小原雄治)は、我が国として重要なバイオリソースを全国のNBRP中核的拠点(現在30)で収集・保存・提供するプロジェクトだ。この総合窓口&情報センター機能を担う国立遺伝学研究所 系統生物研究センターの川本祥子准教授は、本年度から前任者を引き継いで、「生物が違うと、同じ遺伝子名でも意味が違うといったように言葉や文化が違う。生物種を越えて検索できるようなデータベース」を目指す。「そのためにはすべてのゲノムが読まれ、比較ゲノム解析ができている必要がある」と川本准教授。遺伝子に横のつながりができれば、例えば植物では、稲・小麦・大麦などの単子葉の植物で、成功した育種を他の種でも成功させようという時などに威力を発揮する。また動物では特に「ヒトの疾患の解明に伝統的に使われてきたマウスやラットだけでなく、ゼブラフィッシュやショウジョウバエなどのモデル生物を用い、そのシンプルな型を活かして、ヒトの稀少疾患の病態解明を加速させることができるのでは」と期待がかかる。NBRPを通じて「例えば臨床の研究者とショウジョウバエの研究者のマッチングなどのお役に立てれば」と川本准教授は言う。
このほかNBRPは、生態系に関わる分布や環境などの「生物多様性情報」を集めようという国際的なネットワーク「GBIF(地球規模生物多様性情報機構)」の日本ノードとしても活動しており、「ある地域で どんな生物が生息しているかといった データ を登録いただいています。最近では屋久島のクモや近畿で営巣するツバメの調査などの例がある」という。また自身、遺伝医療分野の研究者経験も持つ川本准教授は「いかにデータベースが賢くても、それをどう使ってもらうかという問題意識は常にある」という。特に今後の個別化医療へ向けて「患者さんなどエンドユーザのニーズに、システムとしてどのように応えられるか」といったオープンサイエンス的な視点も採り入れていく予定だ。

(聞き手:池谷瑠絵 特記外の写真:飯島雄二 公開日:2017/08/10)





