チバニアンをめぐって、小説家・伊与原新さんと。
最新刊『八月の銀の雪(2020年)』を上梓された小説家の伊与原新さんをお迎えして、2回シリーズで、研究者との対談によるSPECIALコンテンツをお届けする。第1回目は、2020年1月に地球の地質時代の名称として確定した「チバニアン」の研究成果で知られる、国立極地研究所の菅沼悠介准教授。伊与原新さんといえば、地球惑星科学などの科学の知見を活かした独自の小説作法で知られるが、2人の専門分野はたいへん近く、大学院時代、実は同じ研究室に所属していて、旧知の間柄なのだという。最新作の「雪」と「チバニアン」はどんなふうにつながっているのか?……久しぶりに再会したというお2人にいろいろと語っていただいた。

ゲスト:伊与原 新さん(小説家)
いよはら・しん。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。専門の地球惑星科学をバックグラウンドに、小説を通して、自然科学の魅力を届ける「面白くてためになるエンターテイメント」を目指す。デビュー作『お台場アイランドベイビー』で、第30回横溝正史ミステリ大賞を受賞。2019年には『月まで三キロ』で新田次郎文学賞を受賞するなど、近年、大きな注目を集める作家の一人として活躍中。

研究者:菅沼悠介 准教授(国立極地研究所)
すがぬま・ゆうすけ。国立極地研究所 地圏研究グループ 准教授。専門分野は地質学、古地磁気学。2020年1月、菅沼准教授らの研究グループが提案した地球の歴史上の一時代を指す「Chibanian(チバニアン)」が国際的に認定され、大きな話題となった。南極地域観測隊参加は過去5回、約3か月の氷床上キャンプ体験も持つ。博士(理学)(東京大学)。東京大学特任助教などを経て、2016年より現職。近著に『地磁気逆転と「チバニアン」(2020年、第36回講談社科学出版賞受賞)』がある。
ほぼ1年ぶりに再会して

伊与原:この前お会いしたのは、新田次郎文学賞の受賞の時ですよね。
菅 沼:そうでした。僕らは同じ研究室の出身なんですけど、学年でいうと4つぐらい上でしたか?
伊与原:古地磁気学と呼ばれる分野ですけど、菅沼くんが実験室にいた時は、僕はポスドク(博士取得後の研究員)をしていましたよ、1年ぐらい。
菅 沼:東大で?
伊与原:パリで。
菅 沼:そうでした! で、そのあと一緒にフィールド(野外調査)に行ったりしましたね。
伊与原:ええ、行きました。イタリアに行ったね。
菅 沼:2回行きました。それでその後、伊与原さんはアメリカに留学したので、そこへも遊びに行きましたよね。
伊与原:そうそう。(笑)
菅 沼:われわれ、バックグラウンドはちょっと違っていて、伊与原さんは地球物理学、一方、僕は地質学です。イタリアへ行った時も、僕が地層を調べて、伊与原さんがひたすらサンプルを取るという。
伊与原:われわれの研究分野は、地質と地球物理の境界領域みたいなところがあって、どちらかにバックグラウンドを持つ人が多いですね。
菅 沼:研究分野として、地球物理と地質の境界が、どこかにバシンとあるわけじゃないです。
伊与原:そうですね。物理をメインにやっていた人たちは、やっぱり地質学者の助けがないと、なかなかいいサンプルにめぐり会えないということがあります。かつてプレートテクトニクスが生まれた時は、地磁気の方向を使って大陸の配置を復元するようなブレークスルーに、古地磁気学が大きく貢献したけれど、もうその時代を終えてしまい、できることが少なくなってきているんです。今は他のデータや別の指標などいろんなものを突き合わせていくといった新しいやり方が必要とされていますね。
チバニアン裏話と地磁気反転

菅 沼:ところで、その受賞祝いの時に、チバニアンのことをもっと一般の人に伝えなければいけない、そのためにはSNSをやったほうがいいよって伊与原さんに言われたんですよね。それで僕はSNSを始めたんです。
伊与原:チバニアンがメディアに取り上げられていくなかで、地磁気がどのくらい人々の理解を得られたか、感触みたいなものはありますか?
菅 沼:僕が接した限られた範囲では、やはりあったかと思います。
伊与原:でも、地磁気が逆転するということを、普通の人はまず知らないでしょう?
菅 沼:よく言われるのは、地球がひっくり返ったんですか、とか。
伊与原:自転方向が変わった、とか。
菅 沼:そうですね。たぶんそう思っている人もまだいっぱいいると思うんですけど、それでも少しは認知度が高まったかなとは思います。地球は大きな磁石で、北極がS極、南極がN極なわけですけれども、地磁気の逆転とはそのNとSが逆転することなんです。
伊与原:この間も取材を受けた時に、自分が地磁気のことをやっていましたという話をしたら、それは何の役に立つのかという話になって。ちなみにチバニアンのことも聞いてみたら、その人の中で、地磁気逆転とはつながっていなかった。
菅 沼:つながっていないんだ!……うーん。チバニアンの場合は地磁気逆転に加えて、その当時の環境が氷期、間氷期、氷期と変化したことが詳しくわかることが決め手になったんです。
伊与原:僕が面白いなと思ったのは、僕たちが78万年前と習ってきた前回の地磁気逆転の年代が、今回の成果で77万年前、つまり1万年前倒しになったということです。これは驚きというか、とてもいい研究だなと思った。
菅 沼:もともと地磁気逆転のきちんとした年代(77万年前)を決めたいというのが最初の目的だったんです。そうしたらなぜかチバニアンが出てきちゃったという「ひょうたんから駒」状態!(笑)今後計画されている南極氷床コアの掘削計画で地磁気逆転の時の氷も取れる予定なので、地磁気逆転の年代をしっかり決めてから取りかかるべきだと思って始めたんです。
南極の氷はどのように融けたのか?

菅 沼:南極氷床コアは「タイムカプセル」と言われていて、南極大陸に降り積もった雪氷を垂直に掘削し、主に過去の気象状況を年代を遡って知ることができます。でも、南極氷床の自体の変動についての情報はあまり持っていないんですね。現在、南極の氷がどんどん融けてきて海面が上昇することが大きな問題となっていますが、温かい水がどうやって南極までたどり着き、南極の氷を溶かしているのかは、全然わかっていないんです。もちろん観測は行われているんですけれども、気候には数十年とか長い時間スケールの周期的な変動もあるので、現在の観測からだけだと未来予測が難しい。それで僕らは、南極の岩石や、湖や海の地層から得た地質学的データに基づいて、過去の氷期から現在に至る間に、南極の氷がどんなスピードでどう融けたのかを復元しようとしています。
たとえば今までは最後の氷期は2万年前で、地球上にあったほとんどの氷は1万年ぐらい前までに融けたといわれていたんですけど、南極の沿岸では約9000〜6000年前に一気に融けたことが最近分かってきています。ところがこれは南極の気温が上昇した後の時期にあたっていて、気温上昇は融かす要因ではなさそうなんです。一方、ちょうどその時期に、暖かい水が外洋からすっと南極沿岸に入ったことが分かってきて、この暖かい水の影響で一気に現在の海岸線ぐらいまで氷を融かしたのではないかもしれないと考えているんです。
伊与原:それはだから、もうちょっと内側の露頭(地層や岩石が露出している崖のような部分)を見ないといけない。
菅 沼:そうそう。だから岩盤が何年前に氷から出たのかを、特別な年代測定法や、海の堆積物を使うなど、もうとにかくあらゆるものを使って調べています。つまり──南極の氷が融けるには時間がかかるので、数十年で急にわーっと融けちゃうわけじゃない。でも、一度融け始めたら止まらない。現在の衛星の観測画像の解析とか、今のシミュレーションだけでは歯が立たない。だから、僕らは地質学をやっているんです。地質学から長い時間のデータを調べて、どんなことが起こったのかを理解していく。地磁気逆転も同じです。
伊与原:何だろうなあ……。菅沼さんが僕と大きく違うのは、昔からいろんなことをやる人なんです。それはすごく大事なことだと思うんですよね。手法にこだわる研究者って割と多くて、例えば、自分は地磁気を測っているから、それだけをひたすらやるんだという。そういう生き方もあれば、目的にこだわってどんな手法も使いますという人もいる。これからはやっぱり後者のような研究者じゃないと、なかなかいい成果は出せないんじゃないかな。
菅 沼:僕は単に一つのことを極めることができなかったという……。
伊与原:いや、だからこそ77万年前というのにたどり着いたんだと思うし。
たまたま読んだ英語の論文がヒントに

伊与原:南極へは何冊ぐらい本を持っていけるんですか?
菅 沼:結構持って行けますよ。僕はすごく本が好きなんだけど、小説をたくさん読む研究者は少ないですね。だからイタリアへ行った時も、伊与原さんとは、よく本の話をしました。
──でもその頃、小説家になろうと思っていましたか?
伊与原:思っていなかったです。
──小説家になったと聞いた時、どう思いましたか?
菅 沼:やっぱりなと思いました。イタリアの頃は想像もしなかったけど、本がめちゃくちゃ好きなのも知っていたし、アメリカへ行った時は、小説家になるとは言っていなかったけど、ミステリーについては、俺だったらこう書くみたいな雰囲気がすでにありました(笑)。先日は『八月の銀の雪』が面白かったので、一晩で読んじゃいました。一番印象深かったのは、内核の成長のところ。ごめんなさい、いきなりマニアックで(笑)。
伊与原:いや、内核の成長は、この本の中心テーマですから。しかも、内核が成長しているということは、地磁気逆転よりももっと知られていない(笑)!
菅 沼:内核に降る雪を知っていますか、と問うところが一番印象的なシーンですね。僕も想像したこともなかった。それを「雪が降る」いう詩的な捉え方をしていて、すごく感動しました。
伊与原:たまたまタイトルに「スノーイング」って書かれている論文を読んだんです。著者たちは「雪が降る」という言い方をするんだなと思って。
菅 沼:おしゃれですね。
伊与原:ええ。内核の成長を専門に研究していた先輩に聞いたら、「ああ、スラリーね」と言われて。「懸濁液(けんだくえき)が沈殿して固化するんでしょう」って。
菅 沼:おしゃれじゃないですね(笑)。
伊与原:まあ、そうなんですけど(笑)。
菅 沼:スノーイングのほうがやっぱりイメージも湧きますよね。読んでいて、あーっと思いました。
伊与原:読んだ人が内核みたいな地球の奥底の光景を思い浮かべるために、やっぱり何か感じさせられるような表現方法を探していくわけです。
菅 沼:そこから「内核に雪が降る」へ行くのか、とプロットにも感動しました。
伊与原:ミステリー小説が好きでしたから、もともとはミステリーを書こうと思って書き始めたんです。ところが、なぜかテーマやアイデアが科学のほうへどんどん偏っていった。別に科学を小説に取り込もうと思っていたわけではなく、小説を書くためのインスピレーションを求めていたら、科学へ戻っていった。物語を楽しんでほしいんですけど、その中にせっかくだからちょっとためになることがあったら、そのほうがエンタテインメントとして優れているように思う。科学のことなど知りたくない人が読んで、物語として面白いなと思うその中に、科学をどうやって織り込んでいくかというところが、一番難しくて苦労しているところです。
菅 沼:科学からストーリーを練る場合と、逆の場合と、どっちが多いですか?
伊与原:どっちもあります。その2つがぴたっと合う組み合わせを、ひたすら探しているという感じです。
研究者の世界は世に知られていない

菅 沼:小説の中の人物にも魅力がありますよね。
伊与原:もともとは特別な意図もなくて、どちらかというと単に研究室で起こる事件とか、あるいは科学のネタをトリックの肝に据えたり、トリビア的に使ったりしていたんですが、編集者の方にもっとフラットな小説を書いてみたらと言われて。それで研究者の世界とその外側にいる人たちの触れ合いみたいな短編を書いてみた。
菅 沼:すごくオリジナルですね。
伊与原:意外なことに、今まであまり読んだことがない小説という評価をいただけることが多かったので、ああそうなんだなと。研究者の頭と心の中については、もしかしたら実際に経験を持つアドバンテージがあるかもしれないです。いろんな研究者を見てきて、実に身もフタもないことを言う人だとか、一見嫌なやつだけど本当はすごくすてきな人だと分かる人も多くて、僕はそういう人が好きだし、登場させたいなと思います。
菅 沼:え? (登場人物が)身もフタもないこと言ってたかな……俺はまったく違和感を感じなかった。きっとわれわれには普通だからですね?(笑)
伊与原:ええ。研究者の世界というのは思う以上に世の中に知られてないし、非常識なところもある。「研究の世界の話だというだけで面白いじゃない」って、よく言われるんですけど、そういう魅力的な人たちを描いていきたいですね。
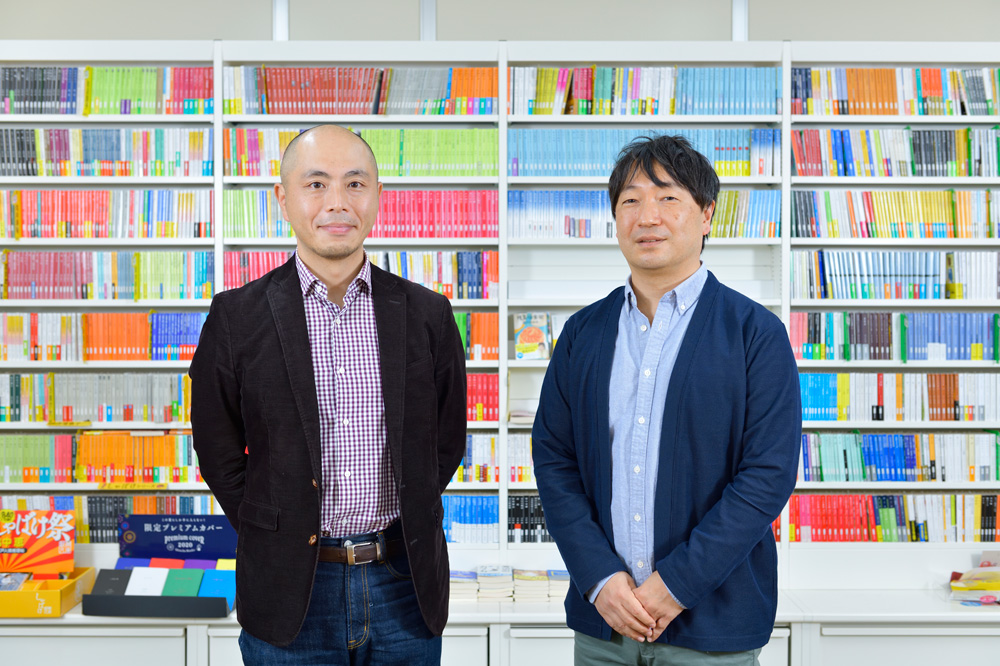
(聞き手:池谷瑠絵 写真:河野俊之 公開日:2020/12/10)




