農業をもっとスマート&オープンに。
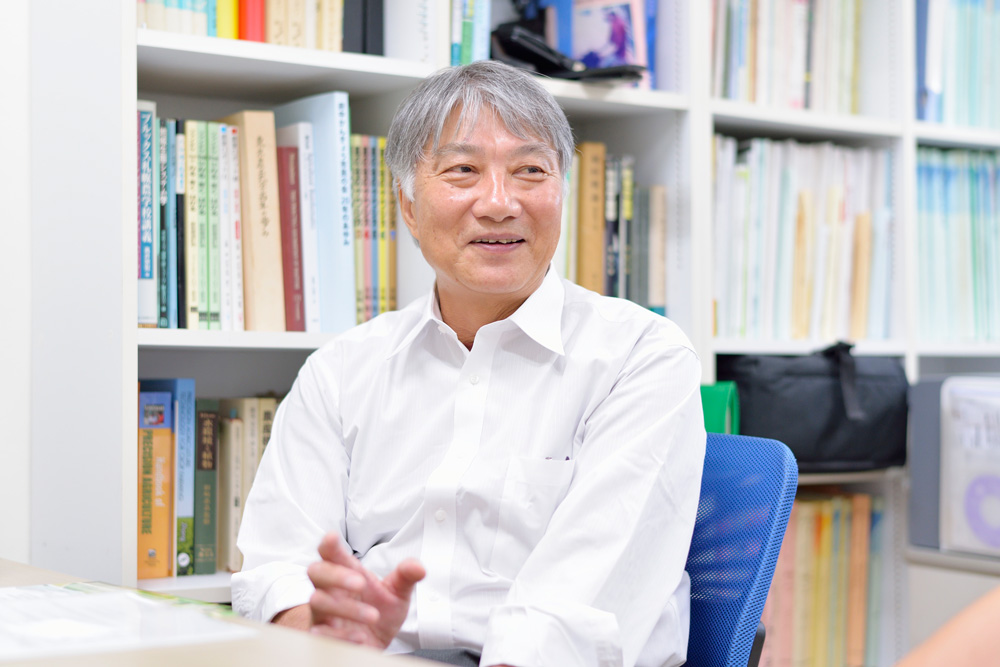
答える人:澁澤栄 特任教授(東京農工大学)
しぶさわ・さかえ。東京農工大学特任教授、日本学術会議会員。1984年農学博士(京都大学)。北海道大学農学部助手、島根大学農学部助教授、東京農工大学農学部助教授等を経て、2001年同学部教授、2004年の組織替えにより農学研究院教授、2019年3月退職。4月より東京農工大学卓越リーダ養成機構特任教授、現在に至る。リアルタイム土壌センサの開発等、ICTを活用したコミュニティベース精密農業の社会展開を推進し、循環型農業の社会実験や、学習する知的農業者集団の支援に注力する。内閣官房政府IT総合戦略新戦略推進専門委員、グローバルギャップ国別技術委員会議長等を歴任。

答える人:大澤剛士 准教授(首都大学東京)
おおさわ・たけし。首都大学東京 都市環境学部 准教授。博士(理学)(神戸大学)。2010年(独)農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター研究員、2016年(研)農研機構 農業環境変動研究センター主任研究員等を経て、2018年より現職。専門は生物多様性情報学。生態学を礎に、生物の分布情報等の環境科学に関わるさまざまな情報のデータベース化を推進し、これらを利用して新たな知見を生み出す研究に取り組む。世界中の生物多様性に関する情報の収集とオープン化を進める国際的取り組みGBIF(Global Biodiversity Information Facility)日本ノードJBIF運営委員。
「科学による農業」の道のり

東京農工大学府中キャンパスには、約15ヘクタールもの広大な畑がある。採れたての野菜は近隣や一般の方々に、恒例の市で、定期的に販売されているのだそうだ。よく整備された均質な土地に見えても、実際の生育の様子や収穫には「ばらつき」があるという。「どんなほ場(田畑)でも、作物がある場所だけ倒れたり、あるいは病害虫がついたりといったばらつきがどうしても生じるんですね。そこで農家の方に研究パートナーになってもらい、農地に計器を持ち込んで、光合成活性や土壌成分などの空間的・時間的な高解像データを集めます」という澁澤特任教授。
約25年前、世界的な動きとして、農家が持つ経験値にエビデンスを与える「精密農業(Precision Agriculture)」が提唱され、澁澤特任教授は日本からいち早く呼応した。「データが示されることで、彼らは確信を持って、なぜばらつきが発生したのか、実はこういう理由があったんだという説明の言葉を見出します。そこからばらつきにどう対処するのか──均質化するのか、あるいは違いを活かすのか──といったイノベーティブな判断が生まれてくる」と澁澤特任教授は言う。「日本も含めて世界の8割は家族型の農業なので、コミュニティが意思決定しなければなりません。その時にわれわれの科学的なデータとその共有が決め手となって、判断をサポートするのです」。
2000年代には、特にGPS(全地球測位システム)をはじめとするICT(情報通信技術)の発達によって農家と科学者のコラボレーションが進展し、2016年には「Society 5.0」を目指す第5期科学技術基本計画の中にも、農業のスマート化が盛り込まれた。精密農業を指す「スマート農業」は、技術革新による収益向上だけでなく、環境負荷の軽減やコストの削減も大きな目標であり、「これらを同時に実現するために必要なのは、農業のマネジメント戦略」と、澁澤特任教授は言う。ちなみに農学を学ぶ学生には、植物の生育を応援したいという者のほか、経営への関心がモチベーションである者も多いのだそうだ。
ファクトを示す数字に無意味なものはない

一方、首都大学東京の大澤剛士准教授は、前所属先の農業環境技術研究所で、それまで表計算ソフトの表で公開されているだけだった国内の農地利用の統計情報を、標準規格である地域メッシュ地図データとして整備し、オープンデータとして公開した。政府が持つ統計データなどの公開をめざす「オープンデータ」は、学術論文などの研究成果やデータの公開に関わる「オープンアクセス」と並んで、オープンサイエンスの主要な要素のひとつであり、大澤准教授はその利用価値に注目する。「葉っぱの数を数えたり虫を捕まえて数を数えたり、自然をつぶさに観察して記録する活動は、博物学(Natural history)の重要な部分です。でも1人あるいは1研究室で取得できる数量には限りがある。一方、政府の調査データには全国を網羅するものもあり、測り知れない利用価値があります。しかも税金で賄われたものなので、ぜひオープンにしてほしいですね」。
誰でもアクセスでき、再利用・再配布できるようにすることによって、新しい利用価値が生み出すのが、オープンデータの大きな特徴だ。「虫を数えている人たちは意識していないかもしれないけれど、再現性、検証性のあるファクトを数字として示したものである限り、1つとして無意味なデータはないと考えています」。データによっては、個人情報のように公開に注意を要するものもあるが、「たとえば専門家のみ公開というのでは、データの開放が不十分」と大澤准教授は指摘する。「どういった条件下で取得されたデータであるかといった情報も含めて提供し、利用者責任で公開する。公共データについては、機械可読な形式でのオープン化を原則とするオープン・バイ・デフォルトであるべき」という大澤准教授の主張は、オープンデータに関わる世界的な認識とも合致する。
大澤准教授はまた、公開した農地データを使ってほ場の区画整備によって絶滅危惧植物の分布にどのような影響があるかをマップに描き出したり、イネの害虫として知られる斑点米カメムシが地球温暖化への応答と土地開発によって東北全域に分布拡大している実態を定量的に示したりといった研究を、縦横に展開する。「科学的関心として、やはり一般に当てはまる現象やルールを見つけ出したい。そのためには、つぶさに観察する一方で、より広域なデータが必要になります」。
オープンデータが農業を開放する

澁澤特任教授によれば、農地は耕作者によって小さく区切られているが、水や風などの環境要因を考えると数百〜数千ヘクタールが1つの単位となる。このため、たとえば有機農業なども、実際には地域全体で農薬をやめなければ実効しないという。日本の農業が市場のグローバル化などによる競争力の激化に対応するためにも、コミュニティがデータを共有する必要性はますます増していると言えよう。
「しかし、これまでは農家ごとの技術とノウハウを、一般的な傾向なのか、産地全体としてどうなのかという視点で情報交換したり、共有したりする「文化」があまりなかったのでは?」と、大澤准教授は指摘する。「インターネットの「フリー」な世界で育ってきたデジタルネイティブの若い世代は、広くデータを公開したり、集めたりすることにあまり抵抗がないのではないでしょうか。農家のデータは、コミュニティの外へ開放されることによって、農業と全然違う目的で使われるといった大きな可能性が生まれます。だから農業のオープンデータと言うけれども、むしろ「農業の」という肩書を外したい(笑)(大澤)」。
では、日本の中で実際に、オープンサイエンスやデータ公開の担い手たちはどのように生まれ、広がっていくのだろうか?「日本のコミュニティは一般に、車座で議論するようなコンテクスト(場)のイメージがまずあって、これをみんなが共有することで意思決定が行われます。定義だとか、誰がどの役割を担うかとかいったことは後で割り当てるんです。オープンサイエンス、オープンデータについても、まずオープンを推進するコミュニティ=場が作られ、場そのものが担い手となって、そこへ人々が参加したい、共有したいというものだと位置づけると、展開が見えてくるのではないでしょうか。そのようなコミュニティがあちこちに生まれ、交流することによってオープンサイエンスが構造化されるように思いますね(澁澤)」。
「オープンデータ、オープンサイエンスという言葉がなかったら、たぶん知り合うこともなかった人たちと出会えるようになり、世の中が動いているのは間違いないと感じます。講演などでは、自戒も込めて「私がオープンデータの専門家ですって言い始めたら、私はもう終わりだと思ってください」と必ず言っています(笑)(大澤)」。

(聞き手:池谷瑠絵 写真:河野俊之 公開日:2019/10/10)




